ヤマハ「ピアノの本」(草思社)に2001年5月〜2002年3月連載(イラスト:峯村良子)
おおらかな価値観で音楽の世界を盛り上げよう
|
|
第2回 「パスカル・ロジェに感謝の気持ちを」 |
“クール”で上品、しかし情熱を失わないピアニズム
最近パスカル・ロジェが好評である。これは我国の識者たちには予想の外だったらしい。ロジェのデビュー盤のリストアルバムでは、ホロヴィッツやベルマンを越える「超絶技巧・ちからワザの豪腕」として紹介されたが、現在では「ロジェこそがもっともフランス的な洒脱なエスプリを兼ね備えたピアニスト」といわれる(書いたのは同じ批評家です)。ちなみにそのリスト盤のライナーノートでは「ロジェの音色が他のフランス人とは違い、きらきらせず、丸っこく太い」と書かれていた。予言(?)は気の毒なことになったが、ロジェの近年の室内楽を含むフォーレやプーランクの録音は、タッチと音色のバランスが良く、クープラン以来のクラヴサンの響きの伝統を感じさせる涼やかさにあふれている。すなわち、“クール”で上品な、しかし情熱を失わないピアニズムが特色である。以前フルートのマリオンとの共演で見せた流麗なフォームは、来日した折りに感じとれず、ベートーヴェンとかを弾いたときなど、テンションの低い様子もあった。だが、パスキエらとの共演したドビュッシーでは、落ち着いた楽想が洞察力と底力を示して、巧みをアピールしていたと思う。
ジャン・フィリップ=コラールの後釜(オールマイティでない分だけマイナーだけどね)になれるのかと期待された彼も、ベロフのスター性に押され、注目度もやがてミシェル・ダルベルト等、若い世代に移っていきがちだった。しかし年齢とともにロジェがより貴族的なフレンチ感覚を鮮明に打ち出すに至って、香りとバランス感に勝るフランスの代表的ピアニストとなってきたことは、本当に喜ばしい。そう・・・・・ロジェでなければだめなのだから。ロジェだからこそ! 私は彼に心からの感謝とエールを贈りたい、なぜ? いや、それはまた後に譲るとして、彼に対して現在日本の評論家が高く評価しているのとは別に、「このすてきなメロディにはもっと艶っぽい表現がほしい」とか「もっと自由にステキにならないの?」等の不満を、殆どの人が持っているのも事実だ。音楽にこめられた情感やストーリー、夢やロマンみたいなものが、彼には希薄だ。しかし、一種この“冷い体温”こそ、フランスのピアニスト達のひとつの流れでもある。そして伝統とは実に価値があり、やっかいで、大切で、邪魔くさい、大変に“重い”ものなのである。
“クール”はフランスのピアニストの伝統?
フランス音楽には、甘美な情景描写や抽象的な心象表現といった、本当は相容れないものが結合して相反する形で内在する。だから、見通しよく表現するために、“クール”な表現こそが最上のものであるとも、私は限定したくない。
もともと「フランスものにはルバートが許されない」等と考えている人もいる。かつてプーランクが自作にルバートを禁じていた。でも、当時はコルトーだの、ちょっと前にはあのパハマンだとかの時代だったのだから、額面通りではないでしょ。事実、プーランクがベルナックと組んだ素晴らしい歌に過度な誇張はない。が、堅苦しさや機械的なビートに支配されることもなく、技巧的に駆使されていても、いわゆる“冷静な音楽運び”とは違う。同時代のパンゼラも、ストレートではあるが、ここに熱い血潮の流れを誰しもが汲み取れる種類の歌になっている。また当時の大作曲家と親交厚いマルグリット・ロンのツボに入った表現は、きわめて自由で、感情的で粋なルバートがさすが(こうしたスタイルは大物ではフランソワ以外には受け継がれていない・・・・・残念)である。続くプーランジェ、ティッサン=ヴァランタン、ルフェビュール、アンリオ=シュバイツァー等は、人間的で暖かく小粋な芸風を示しつつも、同時に“涼やかなピアニズム”の系譜とも無縁ではない。
“クール”なイメージが均一的に浮かびあがるのは次の世代、ステレオレコード録音全盛のあたりからだ。タッキーノ、クロード=ペヌティエ(ドイツものがうまい)、そしてコラール、ルヴィエときて、ベロフ、ロジェ、ダルベルト、続くティボーデ・・・・・と共通項は多い感じだ。往年のR・カザドゥシュは、涙なくしては聴けないようなショパンを実演で聴かせたが、ルービンシュタインの抒情スタイルは否定している。ルービンシュタインの方も「常に意見が合わない私達ですが、ショパンのバラードの1番の最初の主題はルバートをかけない・・・・・という点で一緒です」等と語っている。巨匠ナットも情熱的とはいえ、解釈の基本はスタイリッシュのものにあり、ケンプのソルフェージュ能力を批判していた。近年のルイサダは自由なピアニストとしてとらえられているけれど、先頃のシューマン等を聴いても意識的な個性の捻出であって、内からあふれてくるものとも巨匠の遊び(ホロヴィッツのような)とも違うものなので、表面的な自由さは、やはり“クール”な感覚の産物によるワザといえよう。
ところで、この“クール”という意味合いだが、我々日本人演奏家にもクールな感覚を持つ人はいるし、大体ミスの少ない完成度の高さをめざすスタイルは、当然冷静さの上に構築されるものだ。次元を高くして大家、ベネデッティ=ミケランジェリの場合・・・・“クール”は、何も音色から受ける感じだけから来るのではない。没後続々登場の未発表のライヴの中には「この人何をやりたいの?」と、極めて高レベルは百も承知でも、聴き手を遊ばせてくれない“贅沢なつまらなさ”を覚えるときもある。それでもチェリビダッケとのラヴェルのスゴさ!(カップリングのアルゲリッチのシューマンが、なんとも平凡に聴こえてしまうんだから)・・・・・という訳で、感情移入をあまり行わずに、人を感動させるのは大変だし、スゴいことではある。逆に演奏の質さえ良ければ、磨かれたディティールで誰にでも、ある程度までのレベルを約束させる(感情移入出来たからといって、素晴らしいものになる訳でもないし)とはいえ、感情移入そのものも誰にでもできるモノではなく、それが見事にできる人は、演奏にたとえかなりの傷があっても、偉業と化してしまう魔術が可能なのだ。うーむ・・・・・一筋縄ではいかない。ムズカシーです。
フランス音楽の伝統の上に“新しい風”を吹かせよう!
みなさんはジャン・ドワイヤンの弾くフォーレの全集を聴いたことがありますか? この演奏は数々の賞に輝き、まるでフランスもののバイブルのような扱いを受けてきた。私にいわせれば、音楽の流れは停滞しているし、平板な音色で、冴えもなければ緊張感もドラマも何もない演奏ともみえるのだけれど・・・・・。
でも、このスタイルこそ正しいと思い込んでしまった一部の評論家や先生方のために、実に魅力的に弾く若いピアニスト達の解釈の芽が、どんなに数多く摘まれてしまったことか。この演奏のせいで、ピアニストもまたフォーレを弾く気がなくなっちゃう(元来アルゲリッチみたいな人たちは、演奏効果の高いギャスパールみたいなものを弾くしね)。洒落たロンやレヴィの門下なのだから、ドワイヤンにはもっと気の効いた演奏を期待してしまうが、さらに一世代待って、室内楽の名手として知られるジャン・ユボーによるフォーレ全集にしても、同様の不満を払拭できた訳でもなく、むしろこれで駄目押しされた感もなきにしもあらず。これは教師ピアニストの限界なのか? この周辺のピアニスト、フェブリエにしろバルビゼにしろ、ペルルミュテールにしても、純粋に音だけを聴けばどうなのだろう? 例えばケンプのベートーヴェンも、もし覆面で聴かされたら軍配は? ポリーニとどちらに上がるでしょうか?
しかし、ことはそんなに単純ではない。平たくいえば伝統の重さというものが、プラスアルファとして必然性と説得力を持っている。例えば私たちがベートーヴェンの演奏に悩み、立ち直れないでいるとする。その時、もし老ケンプがかたわらでほほ笑みアドヴァイスしてくれたら、きっとそれだけで救われるだろう。でも、もしポリーニが横で笑っていたら? その時は、馬鹿にされた気分がするかもしれない。それは上手下手の問題ではないのだ。(今回のポリーニの来日時、高価なチケットが当然のようにソールドアウト、でもイギリスでは1500円だったのにガラガラだった)
実際にドワイヤンやフェブリエに師事した人の話を聴くと、あの当時のレコーディングはひどすぎると口をそろえる。先生たちのあの魔術の様なニュアンス、間の取りかた・・・・・そんなステキなものがレコードでは全部失われて化石のようになっている、ということだ。じゃあ、やっぱりあの録音マズイんじゃん(笑)。マズくとも同時にドワイヤンの存在自体は否定できないということだね。逆に我々日本人ピアニストが、どんなにアイデアに溢れた素晴らしい演奏をしても、それで現在の批評家・先生方・一部演奏家たちに、その信仰の転換を求めるに至らない・・・・・。それは、そんな演奏を“新しい風”として聴いてくれないから、―伝統に対しての不正解な表現としか感じてもらえないから。
そもそも“伝統芸術である音楽”にあって、伝統は柱なのだから否定できない。悲しいがいたしかたないことなのだ。フランスものではブレンデル、アシュケナージ、アルゲリッチ、キーシン・・・・・でも、やはり無理だ。だがロジェなら・・・・・できる。けっして皮肉ではない。彼はドワイヤンのつまらなさも、“冷たい”味気なさも受け継ぎながら、それでいて先達からは1歩進んだ自由さをみせている。批評家たちをかわして、まさに“風穴”を開けてくれたのだ。がんばれェ〜、伝統を受け継ぐフランス人ロジェ!
そしてみんな彼に続いていくふりをして、好きなことをやりだしましょう。そしていつか芳醇なワインのようなステキなフランス音楽を・・・・・乾杯!!
|
第3回 「ラフマニノフに原典はないのか?」 |
これだけは、ヤメテよね!!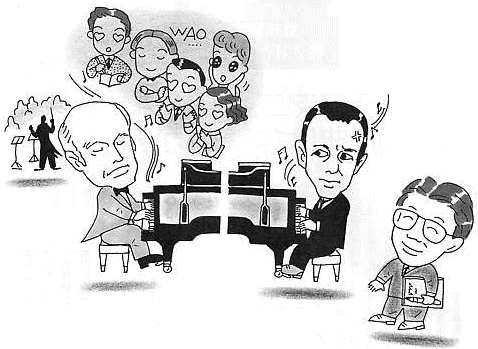
先輩ピアニストのOさんがシューベルトの夕べをひらき、ある批評家に「これはシューベルトでない。私はシューベルトを聴きに行ったのであって、Oを聴きに行ったのではない」と酷評された事があった。
これは私にとっても、最もショックな批評の1つだ。何の権威があって「これがシューベルトだ」と言い切れるのであろうか、不思議だ。いろいろな個性的な演奏があるから楽しいのだし、勉強すればするほどその深さに畏敬の念を覚えるだけなのに、この浅はかさにどう対処したらいいのだろう、さすがにひどいと思った。
Oさんはこの後、活発な活動は控えてしまった感もあり、本当に残念だ。好き嫌いは誰にでもあるが、嫌いなものは書かなければ良い。彼女のファンだって多くいるのだから、またしても私たちは大切な聴衆を失ったのである。この繰返しが業界の低迷を呼んでいることを、評論家は心すべきでしょう。
だいたい演奏会を執筆料を稼ぐために同じ時間でかけもちして、片方(たいてい若い人の方)は後日テープで聴いて書くとか、大演奏家の場合でも大新聞の批評欄に当日演奏されてない曲の絶賛が載せられていたり(つまり演奏会に行ってない)等と、そんなひどい日常を演奏家が悪く書かれることを恐れて黙っているのよ〜。田中真紀子さんじゃないが、正義であっても戦うのは大変だしね。
演奏家も確信犯?
さて話は戻って、Oさんのような、評論家にこの手の批評を書かれる時は、演奏する方も最初から覚悟している場合が多い、つまり確信犯なのであります。
私の場合は、大キライなシューマンの《女の愛と生涯》を伴奏した時のことだ。嫌いなワケは、描かれている女性像があまりに愚かで情けなく、完全に女性は男性のために存在する生き物で、単細胞だと宣言しているかの如くのストーリー、こういう男女の区別・差別をつける手合いには、名曲でも心から憎しみを覚える。
そんな時、今は亡き父(藤原歌劇団創成期のバリトン歌手だった)が「この曲集は1曲1曲の間に1年とか2年ある・・・・と思うと、主人公の女性が理知的に見えてくる。つまり曲と曲の間を少し間をとるだけで、かなり品格が違ってくる」と教えてくれた。シューマンの歌曲集は《詩人の恋》のように、いろいろな環境での雑多な感情が曲に転じてちりばめられることが多いので、曲間をあけない事で一貫したスタイルが確立される。だがストーリーを持つとなると別問題だし、この女性主人公の名誉のためにも、である。
と考え、コンサートでキッチリ間をあけた演奏をしたが、これがオペラ界の重鎮のH先生にシッカリつかまった。むしろH先生ぐらいになると、こうした解釈の相違は絶対に見逃すことはないのだ、さすがです。「曲間をあけたことでシューマンの連作歌曲の意義が損なわれた、斎藤はシューマンを知らない・・・」と。
でも私は確信犯、そう言われても今でもこの解釈を変えるつもりはないのです。そして「シューマンを知っているのか?」と聞かれれば「知らない」と答えてもいいと思う。なぜなら私が大切にしたいのは目の前にある美しい曲と、その女性のことだけだから。「シューマンを知っているが女性を知らない」等と思われる方がよっぽどイヤだし、ま、父親譲りの心意気といったところか。もっともH先生とウチの父親は親しい友人関係にあるので、そういう斎藤家の家風を充分知った上での批評かも!? 単なる巻き添えを受けた息子だったら・・・・・もっとやだなぁ(笑)。
 ラフマニノフなら見て見ぬふりか?
ラフマニノフなら見て見ぬふりか?
そもそも「これがシューベルト」だとか「これが正道」としてとらえられているものは、もともと1つ厳然と存在していたものではなく、いろいろな演奏家の演奏の積み重ねによって淘汰され、解釈・イメージがおぼろげに定められてきたものである。けっして机上の空想からではないはずだし、現在どんなに偉そうなことを言っても、誰もシューベルトやシューマンに会った人はいないのだから、単純にこだわればこだわるほど逆にサギっぽい。幅を持たせていろいろな可能性を探る意味でも、現在でも学問化せず、演奏家が新しい解釈を試行錯誤すべきなのであり、それによって原典のイメージがより高められ、浮き彫りにされていくのではなかろうか。
不思議なのはラフマニノフだ。ラフマニノフは大作曲家であると同時に、まれに見るピアノの達人であった。その技術は現代の我々が見ても抜群であり、コルトーのような不満足な要素は存在しない。それは何を意味しているかと言うと、彼は自分の作品を弾くのに自分のイメージを忠実に描ける技術を持っていたということ。つまり彼は思った通りに自作を演奏している・・・・・まさにラフマニノフは自作の曲のあるべき姿を指し示しているのだ。
ところがたとえば、誰もリヒテルの弾くラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を袋だたきにしていない。リヒテルはこの曲を誰よりも遅いテンポで始める・・・・・非常に内容が深い一世一代の超名演だが、ラフマニノフの演奏とは違い過ぎる。なぜ批評家は「これはラフマニノフじゃない。私はラフマニノフを聴きにきたんだ、リヒテルじゃない」と言わないのだろうか?
リヒテルだけではない。誰もラフマニノフみたいには弾かない。唯一往年のレナード・ペナリオが、ラフマニノフを意識したルバートを使っている。でも「これだ。これがラフマニノフだ」とは言われてないし、むしろ知らない人の方が多い。なぜだ? リヒテルの演奏がどんなに優れていても「そんなものは邪道だ、認めてはいけない」と叫ぶのが、今「これこそ正道」を叫ぶ評論家のやっている"お仕事"だ。
だが実際には、演奏や映像が残っている作曲家には、はっきりとその原典の実像が見えているにもかかわらず、作曲者自身の解釈は軽視してしまうのが実状だ。R・シュトラウスやストラヴィンスキーの自演に至っては珍品扱いだよ。たとえ万が一演奏そのものに魅力がなくても、それが原典というものではなかったのか? それを徹底分析して確固たる解釈やイメージを示すことができずに、バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ショパン、シューマン・・・・等々何の実体もない大作曲家の幻影ばかりにこだわり、「これが正しい」とは何の根拠なのか? 形が遺されていないから言える・・・・・まさに「死人に口なし」では、いささか卑怯な姿勢の様にも思えて腹立たしい。
ラフマニノフが自由ならシューベルトも自由。シューベルトに原典があるのなら、ラフマニノフにも原典がなければウソだ。もしそれらが「古いスタイルだから・・・・・」等と言うのなら笑止千万、それこそ原典の否定だし、バロックであっても時代考証や歴史感、様式も楽器の選択も必要なくなる。ラフマニノフがモイセイヴィッチやホロヴィッツの演奏を認めていたので、自作の多様な解釈の容認は許される? 以前私も別宮貞雄氏の作品を弾いた時、作曲者の指示から逸脱する演奏をして、逆にご本人から絶賛されたことがあり、その後も楽譜を送っていただいている。批評家なら「それは違う」と吠えるだけだが、作曲家が現存なら受け入れてもらえることもあるのだ。
さらなる可能性に向けてがんばるのだ
だから評論家も近年の作曲家・現存の作曲家に関しては、世間の評価の確定を待ってからということなのだろう。演奏によって何回も実際の音にされたのを聴き、演奏家たちの一通りの解釈の施行錯誤を待っているのである。つまり評論家は瞬時に作品や演奏の価値を決定づける能力は持ち合わせていないし、わからないという事が証明される。
演奏解釈の正道は演奏の歴史なのだから、我々・今の演奏者にこそ、そこに解釈を重ねていく権利があるのだ。演奏家は勇気を持って、さらなる可能性に向けて試みを深める必要がある、がんばりましょう。そしてその歩みを乱す、筋の通らぬ執筆活動こそ迷惑であり、代わりに新しいユニークな若い才能を発掘することに御助力いただきたい・・・・・これこそが求められることだろう。
|
第4回 「悩み多き日々なれど音楽をやめず、あきらめず、生き抜きたい」 |
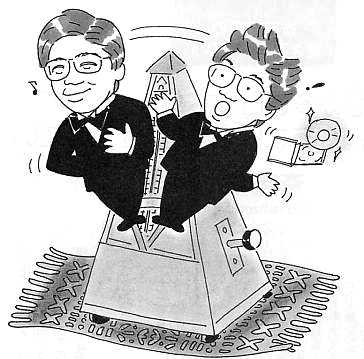 実力プラス「何か」を持つ
実力プラス「何か」を持つ
私はNHKでアマチュアにピアノを教える番組をやっていたせいもあって、アマチュアの方々とも実に気軽にお話する機会が多く、うれしい。さて、アマチュアに限らず、ピアノを勉強する上で最も大切なのは、「やめないこと、あきらめないこと」というのに尽きる。事実この「やめないこと」というのが、本当に難しい。音大を出てもササと結婚してしまい、演奏活動等見向きもしない女性もいれば、生活の安定のために望みを捨てる人もいる。ストレスに絶えられない人もいれば、才能と運に見放されたと思い込み、転職をはかる人、また活躍していても大学の教授になって自然に演奏会が減ってしまう人や、技術的もしくは人間関係的に若い連中についていけないことを悟る人、チケットさばきや営業に疲れてしまう人・・・・・当然いくら「あきらめるな」と言っても、食べていけない現実が目の前にあれば、どんな勇気も通じない訳だし。
そんな中にあって地方の私立大学に通う音大生には、とかく抱きがちなコンプレックスを取り払い、あきらめることなく自分なりの精進にて、自分なりの大成のみを考えるようにと、私はいつも話している。実際舞台に立てば「うまい下手」よりも、聴いて下さる方々に直接訴える「何か」こそが必要となり、それが受け入れられれば、学歴・賞歴などは全く無意味なものとなる。チャンスは思わぬ所にころがっているものだし、世の中も多様化しているのだから、いくらでも受け皿は存在するはず。・・・・・その「何か」さえあれば。
「何か」と言えば・・・・・私は第2期?スランプ時代に、調律の村上輝久さんに「斎藤さんには“なぜか”熱烈なファンがいるんだよね」と言われて、さすがに傷ついたことがある。そしていつか出世してこのオヤジ(失礼!)に「村上さんて“なぜか”ミケランジェリに気にいられてるんですよね」と言ってやる(笑)と思ったのだが、ある日ハタと気が付いた・・・・・「なぜか気に入られる」というのは、はっきり何だかわからないんだけど、認めざるを得ない凄い「何か」を持っているということだ。もちろん、調律の神様と言われる村上さんが、さまざまな技術的な点でリヒテルやミケランジェリの要求に応えられるのは当然だが、それを超えた「何か」がなければ、天才芸術家のお気に入りになど、なれる筈がない・・・・・つまり私への言葉は最大の応援メッセージで(にこやかだったしネ)、それがわからない私こそが未熟者でございました。すみません。今も時折お会いする事があるが、いつも優しい眼差しで、私達ピアニストを支えてくれる人である。
高嶋音楽事務所の高嶋社長にお会いしたとき、「スポーツならば100メートル9秒を切れば勝ちだが、音楽だと100メートル12秒台でも勝てる事がある」とお話されていたのが印象的だった。だが、「実力」「聞き手の好き嫌いの主観」プラスこの「何か」が、評価というものを複雑にしていく。ゆえにその「何か」を持つことこそが、この世界を生き抜く力の根本であるといえる。自分だけのオリジナリティを持つ人の心を射抜くパワーが、演奏のみならず人生の生き方にも前向きに現れるべきだということだ。
矛盾した感覚に悩む
ところが、生徒がたまたま1度の舞台で成功したのをいい事に、いきなり国際コンクールを受けるとかCDを出したいとか言いだすと、「ちょっと待て」と苦言を言ってしまう・・・・・「やる気と前向きな姿勢」を誰よりも奨励して、理解している私のはずなのに。
子供がレッスンが急に楽しくなって調子にのってくると、「ちょっと待て!」と・・・・・やはり言ってしまう。音楽の楽しさを早く感じて、暴れて欲しいと思っていたのだし、彼らをそういう気分にさせたのも私なのに。
またある音楽家の集まる場で理事をしている人が、たまたま地方の私立短大の出身で、そのためでもないのだろうけど、芸大出身の他のメンバーから何かと意地悪をされる等という話を聞くと、「やっぱりもっと気を遣った方がいいんじゃない?」と答えてしまう。聞こえは良いがその台詞の後ろに「彼らはあなたよりももっと努力して芸大にはいったんだし、自分でもあなたよりはうまいと思ってるんだから、対等な顔をしてはいけないよ」という、とても嫌悪すべき差別的な考えが無いとはいえない。最悪じゃないか。普段言っている「そんなことを気にせず、前向きに。音楽の前ではみんな対等じゃないか!」という言葉がなぜその場で出てこない?
アマチュアの人がコンクールを受けたとき、彼らが「結果はどうでもいいんです。楽しんでいるだけです」と言っているのに、「それは嘘でしょう。絶対うまくなりたい、賞をとりたいという気持ちがゼロだったら、ここにはいないはずです。逃げずに賞をとりたいと正直に言って、それに沿って選曲や勉強すべきだ。舞台ではプロもアマもないんです」等と言ったのも最悪(笑)。日ごろもっと音楽を楽しむことを自分でも実践しているつもりだし、人にも勧めているのに。
それから「ベートーヴェンのソナタを1曲も勉強してないのに、気軽にピアニスト等と名乗ってはいけない」なんてことも言った。人を傷つけるつもりもないし、大体そんな偉そうに言える立場でもないし、自分では音楽愛好家に最も近い存在のつもりで、若い人の味方を自負して、少しでも音楽市場が活性化できるようにと考えて、こんな連載もしている・・・・・でも自分の心の中にも、閉鎖的な矛盾する感覚が生きていることを知り、悩める日々である。
解決はしないけれども

自分なりの弁明で考えると、1つの原因に「先入観」というものがある。「自分がこれだけ苦労してきたんだから、そんなに甘くはないぞ」という感じだろうか、特に受験から始まった毎日毎日の苦労を考えると、ついついそんな気分になる。だからこそ若い人にはあまり苦労をさせないようにと思うのだが、自分の実体験がからむと、こちらの気持ちも単純ではなく、親身であればあるほど、余計なことも言ってしまうのだ。しかし、年とともに達観できなければいけないと反省・・・・・なぜなら多分にこの世界の「生き残り戦争」は、気分や勢いの問題でもあるので、苦言を呈してブレーキをかけさせるのは、大きなお世話なのである。
先入観といえば、たとえばホロヴィッツやルービンシュタインが自分の好きなある曲を弾いているということを知ると、きっとこんな風だろうなと連想したりするでしょう? これは演奏を聴く楽しみの1つだし、そういうイメージが持てるからその演奏家のファンにもなれる訳だし、その予想が当たってもはずれても、聞き手としては何かうれしい気分になったりする。でも本来音楽の聴き方としては、こうあってはいけない。だから一旦悪い印象を持つと、実際は素晴らしくても、その演奏家の演奏がなかなか受け付けられない事もしばしばで、これは非常にマズイし大変不幸なことである。私はよく輸入盤を売っている店で、名も知らぬピアニストのCDを頻繁に買うが、中には驚くほど上手な人がいて、情報や先入観がないだけ感動も大きい。しかし先入観にそれだけのパワーがあるならば、逆にこれからの演奏家は自分なりにイメージ作りをしなければいけないのだろうし、それは現在においてはコンクールの勲章1つ増やすよりも重要だ。
私もJクラシックと呼ばれるジャンルからCDを出したが、もう私のようなオジサンだと、イメージ云々より自分でジャンルを広げることを楽しんでいる感じで、むしろそうした場所に身を置けるのが心地よい。が、そこでデビューをはかる人たちは、そのJクラシックのイメージと自分の理念との両立に戦いがあり、大きな飛躍を生む力を次に向かって放出できたり、埋もれてしまうこともある・・・・・しかしそれは実力云々というものではない、イメージ戦略の攻防の結果というのが非常に現代的であり、それを空しいことととらえる人たちも多い。当然本来のあるべき姿でもないわけだが、自分の若い頃を考えると、そこに集う若者のエネルギーはずっと大きいのだから、私は肯定的に見守りたい。
世の中が移り変わり新しい世代が頂点に立つとき、少なくともつまらない体制的な悩みは払拭されるだろうが、みんなが音楽の前に対等に前向きに立ち、そして演奏のチャンスを多くつかみ、生涯にわたって演奏し続けられる本来の願いが成就されているかどうかは、わからない。みんながあきらめなければ叶う・・・・・と思うのは、まだまだ甘い? 具体的でない「何か」を心に持ち、前向きに大きなエネルギーを失わず・・・・・となればそれは所詮個人的な戦いでしかないのかもしれない。でも私たちも自分の出来ることを精一杯やっていき、少なくても心がけを持っていれば、わずかでも素敵な社会がひらけるはずだと思っている。
|
第5回 「こだわりは美徳にあらず」 |
風の中の羽根のように・・・・・オタクごころ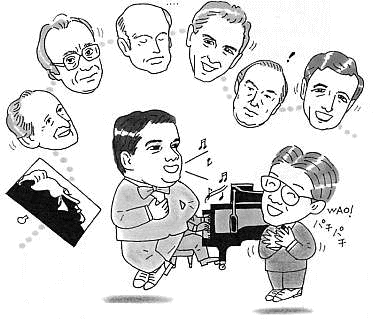
ホームページが何かと誉められて「自分で作るんですか?」と質問され、「ファンの人が作ってるんですよ。大体ホームページを熱心に立ち上げる男なんて、モテない奴に決まってますよ」と答えれば、一時代前なら大受けだった。時とともに、もうコンピューターはオタッキーな世界ではない、日常のものになりつつあるが、クラシックファンの中には本当の「オタク」と呼べそうな「つわもの」たちがまだまだイッパイいるのではないか。そしてこの「オタクファン」を多く抱えるジャンルほど、その音楽ジャンルの衰退度も大きいようで、クラシックやジャズ、シャンソン等々・・・・・業界を活性化させようと思えば、「オタク」は一つの障害になりえるのだ。
実は私も中学生ぐらいの時は評論家気取りで毎日のようにスコアを眺め、さまざまな演奏を自分の短い物差しで測って書いたりしたので気持はよくわかるが、今にしてみればこんな感想文の製作ほど恥ずかしいものはない。この「オタク」行為は、本人がその気になっている分とげとげしくもあり、音楽を愛する行為からは逸脱してしまう。結局、何もわかっていないから書けるのであって、わかっていたら自分が演奏した方がよいことに気づいて赤面するのみだ。まあ、もっとも「オタク」とはこだわりを持つ人々の意味なのだから、演奏家の方も立派な「オタク」である(笑)。だから演奏家にまじめな人生観・音楽観を語らせると、それなりに気絶もののポリシーをいやというほど披露してしまうことも少なくないのだが、それを積極的に話したがる人はあまりいないので、演奏解釈や音楽について論じるのが好きな演奏家ほど腕は悪いという説も出てくるわけだ。
ヴォーカルの大御所トニー・ベネットは「円熟」ということについて「“彼女が好きだ”と、100個以上の言葉を使わなければ伝わらなかったのが、“LOVE”というたったひと言だけで表現できるようになること」と言っている。確かに、優れた巨匠の演奏ほど究極的に“楽しい”とか“悲しい”とか“苦しい”とか……人間の根本的な感情と音楽を、大きく一つに捉えたエッセンスで表現しているものだ。一般に芸術性が高く、完成度も高い、磨きのかかった演奏には感心し、感動はするが、なかなかに一緒に号泣したりはできない。「オタク」のこだわりは単純な感情とはかけ離れた細部へのこだわりが主眼となるので、この辺りの理解は苦手なはずだ。アマチュア・オケの人でよくマーラーとかブルックナーの「あの小節のホルンが・・・・・」って一晩中論じられる人を知っているが、これもまた本当に音楽を愛していることではないと私たちはいつも実感している。そういえば私はアマチュアの方々と共演してうまくいかなかったことが結構ある。それは彼らが口ほどに腕が良くないからだ・・・・・等ととられてしまっては超心外。情熱も知識もプロに負けないし、アマチュアピアノコンクールのレベルの高さにも本当に驚かされる。原因はこうした音楽の愛し方、空気の違いといったところだろう。
「伴奏」をなめたらいかんぜよ!
よく誤解されるが、大演奏家や世界的な巨匠とアンサンブルを重ねていると、苦労が多いと思われがちである。ところが実際はこれほど気楽で楽しい仕事はなく、少ないリハーサルでバッチリ合ってしまう。相手は理想的な解釈で音楽的な問いかけを演奏で示してくるので、それに自然に答えればいいだけである。相手の演奏を聴けば次に自分がどう出なくてはいけないのかがはっきりわかり、そこでアイデアのある対応ができれば音楽に遊びが生まれ、無上の喜びも味わえるというわけだ。(ただしもとの正統的な解釈を知らないと簡単ではないが)。お互いの間にそうした空気を作ることができれば、もうこれは何をやってもOKである。
やはり大切なものはエッセンスであり、みんな実にシンプルだ。そして、こだわりを捨てたニュートラルな姿勢・・・・・ニュートラルとは個性を抑えるという意味ではなく、どちらの方向に転んでも自己を出せる準備状態のことを意味している。ソロも伴奏もアンサンブルもまったく同じものだ。クラシック音楽の根源は室内楽なのだし、ソロよりアンサンブルの仕事の方がつまらないとか可哀想とか、もし低く見ている人間がいたらこれはもう音楽をやる価値はない。また、何かと気遣いの多いのがアンサンブルと思っていたら、これも誤解である。常に自分を主張し、お互いに対等で、けっして遠慮しあうものではない。もし片方が負けている感じがしたら、それは絶対に負けてる側の実力不足。遠慮して負けてる方に合わせてどうするんだ?
たとえば、名バリトン歌手フィッシャー=ディースカウは非常に面白い試みをしている。彼はジェラルド・ムーアという“伴奏ピアニストの神様”との一連の録音の後、リヒテルやブレンデル、ペライアさらにポリーニやホロヴィッツとも録音を残している。特にポリーニとの《冬の旅》、ホロヴィッツとの《詩人の恋》は、他流試合がごとくの面白さ! ところがである、このリートの達人が四苦八苦している姿に、多くの人は「ポリーニやホロヴィッツはソリストだから、歌の伴奏には向かないし、下手だ」と解釈してしまうのである。これは本当に大きな誤りであって、ポリーニにしてもホロヴィッツにしても、いつも通り自分の音楽を立派に構築しているだけで、これは芸術家として最も正当な姿にほかならない。むしろ太刀打ちできなかったディースカウの方が悪いといえば悪い(笑)のであって、最初からポリーニの「とぼとぼとわびしくみすぼらしい冬の旅」は想像できないし、ホロヴィッツのシューマンが即物的であるはずもない。当然多才なピアニストが来れば、名歌手といえども主役の座はおびやかされるわけだし、ディースカウもそのスリルを愉しんだはずだ。
最も残念なのは、主役の座を奪われるのを恐れた一部の実力イマイチの歌手が、自分よりもさらに能力の低いピアニストを指名することが多い日本の現状・・・・・そしてそのピアニストは伴奏の名手として祀りあげられる。そのピアノ弾きが伴奏とはかくあるべきだみたいなことを言い、ソロとは違った特別な才能が伴奏には必要だと語ったりする。これは保身から生まれた、ちょっと悪質な「こだわり」である。本当に悪いのは歌手の方かもしれないが、それでも彼らには「ベートーヴェンのソナタが弾けないのに歌の伴奏等してはいけない」と言いたい。つまらんウンチクはまずピアニストとしてのレパートリーが網羅できてからのお話し。特殊な訓練を受けなければ伴奏が弾けないなんて・・・・・ドイツリート、日本歌曲なんか特にうるさく言われるが、もっと多彩にやりましょうよ。“特殊”だってことは“つまらない”ってことだよ。みんな同じ「自由で素敵な音楽」にしたい!
クラシックなピアニストのこだわり
さてこれもこだわりの一種だが、ジャズやイージーリスニングのピアニストの演奏がどうしても心から味わえない・・・・・というクラシックピアニストの病気についてである。実は私にも多分にそういう傾向があるので、何とも情けない。どうしても「腕に力が入ってるだろう」とか「そのタッチはなんじゃ?」みたいなノリになってしまい、ついつい「ちゃんと弾いてクレーダーマン」と癒しの音楽どころかイライラの原因になってしまう。あの素敵なビル・エヴァンスのピアノにすら、底の浅いパコパコの印象を差し引いて聴くのに、大きな努力が要る。しかし逆にジャズメンに言わせたら、我々の弾くムード音楽も、大いなる努力が必要な鑑賞物に違いない。
だから話題のアファナシエフは面白いのだが、やはり彼を高く評価するのは演奏家よりも、批評家とオタクの方々に集中してしまう。なぜなら、クラシックピアニストのこだわりに従って聴けば、こうなる。まずピアニストとしての質は、同じような強引な解釈で聴かせるピアニストのイーヴォ・ポゴレリチと比べたら天と地の差。ポゴレリチのあの美しい音と透明感のある音のバランス感は、ピアニストとして極めて上質である証明だ。遅めの内省的な解釈でクラウディオ・アラウのブラームスと比べたら、そのレガートと歌の一体感、情感的な要素等どれをとってもアラウの方が問題外に優れている。次に音量は・・・・・といったふうに、ピアニストであれば瞬時に、そのピアニストの質を肌で感じてしまうのだ。
これは何とかしないといけない。結局「究極の音楽的なもの」、最初に書いた「単純な感情のエッセンス」等、最も大事なことが聴こえてこない可能性もある。たとえ無意識であっても、これもこだわりには違いないだろうし、捨て去るのもまた困難である。みんな音楽が好きなのに、好きなために何かつまらないことにこだわって、視野を狭めてしまう。恋は人を狂わせるものとあるが、音楽もまた人を変わり者に仕立ててしまうのか。うーん、吼えたところで解決のできない問題のような気もするなあ。
|
最終回 「また温和な人に戻るとするかぁ〜」 |
演奏もまたビジネスであるということ
この連載もはや一年、いよいよ最終回である。これを始めたときには、随分周囲から心配していただいた。歯に衣着せずにいろいろ言えばしっぺ返しも多い・・・・・特にこの連載では旧体制派の考え方に物申すのであるから、風当たりはなおさら強いはずだった。しかし多くの共感をいただけたのは、今のクラシック界を何とかしなければという危機感と、自分だけが良ければいいという個人主義ではもう済まないぞという感覚・・・・・言うべきことは自身のマイナスになっても言って戦う・・・・・と皆さんが感じておられたことを再認識して、私も大きな意義を感じた。
さて演奏家の戦いといえば……演奏で生活していくという難しさ、音楽を深めたりレパートリーを広げること、テクニック的な問題や暗譜に関してのこと、生き残り競争と足の引っ張り合い、批評家や心ない人たちの雑多なコメントに対するストレス等々……と、数え上げれば確かに大変そうだが、これはどの職業にだってあてはまること。そもそも演奏家には、音楽を精神道のようなイメージでとらえる傾向が強く、ビジネスとしての認識が足りないのではないだろうか。確かに、音楽にはどこか神聖なものがあると信じているからこそ、譲れないプライドもあるのだし、厳しい修行にも耐えられる。でも、それがネックになっては本末転倒だ。演奏家も、自分の職業をもっとビジネスライクにとらえ、業界の活性化を皆が意識するようになれば、お互いに役割を認め合い、自分のやるべき道を見つけて、つまらないジェラシーや焦りもなくなるだろう。戦う相手もおのずから異なってくるはずと思う。
未来を見越し、音楽業界の発展を考えて
音楽家の縦社会も悪例の一つ。学生は自由に先生を変えられないでしょう? 好きな先生について、見聞を広めるためにさらにたくさんの門を叩きたいでしょう? でもそれがしづらいなんて、どう考えても変・・・・・例えば音大で、生徒に先生の選択権があり、籍があっても生徒を持てずに給料ゼロの先生もいたりする・・・・・そこでは演奏家のレッスンもダブって受けられるし、相性の悪さを理由に生徒が先生を変えられる。コンピューターによるネットワークや、即戦力になりうる演奏家を発掘するための試験やオーディション体制も整備され、ホールの建設でも立地条件を考慮し、地元と音楽業界双方の活性化を図っている。こうした考え方をすると、「商才に長けている」と陰口されがちなのだ。本来、何事もこうあるべきはずなのに。逆に、ショパンの小品一曲すらろくに弾けない教授が、空威張りの権威を振りかざし、己の利益と出世のための人事とセクハラ、おまけに大曲を持ってきた生徒にも短いレッスンしかしないような音大だったりすれば、そこに内面的に活気ある未来を見出すことなど到底できないと私は考える。
以前、某評論家が「悪魔に魂を売ったカラヤン」と評して、カラヤンの商業主義を批判したことがある。しかしカラヤンがいなければ、ビデオ、レーザーディスクそしてDVDへとつながる現在の流れは生まれてこなかった訳だし、評論家にも利益がなかったはず。またカラヤンの音楽そのものも、時を経て改めて聴き直すと、そこに書かれていたような表面的な薄っぺらさを全く感じない。評論家が自分の好みでものを言うのは結構なことだが、やはりプロならば未来を見越して、さらに業界の発展を考えて発言をすべきでしょう。それを「自分の感性や見識を犠牲にしてまで、することではない」と言うのなら、仮にその感性や見識が素晴らしいものとしても、それを演奏して「こういうものです」と示すことができない以上、机上の論理か幻に過ぎないものだということを認識していただきたい。事実、「こういう風にしたら素敵だろうな」等と思った表現が、実際にやってみたらひどく陳腐だった例はいっぱいある。失礼な言い方だったかもしれないが、ここは柔軟であるべきだと思いますよ。もともと「言葉では表現できないから、音で表現した」ものを、また言葉で表現し直そうとしていること自体が不思議なことなのだから、自らの存在意義を、何をすべきかを考えて欲しいのである。音楽に携わる者それぞれが一つの歯車となって精進し、業界自体を回転させていかなければ、権威自体が空洞化してしまい、無用の長物にもなりかねないのだから。
クラシックを扱う雑誌は今日、まず黒字ではないだろう。そんな中で権威を謳い、批評をメインとした雑誌は、最近の情報誌に押され気味だ。情報誌は聴き手にも重要だが、演奏家にとっても営業宣伝媒体として最も大切だし、利用価値が高い。また、情報誌は紹介記事と商業広告がメインとなるので、悪意も少ない・・・・・良い意味でのヨイショは、今の業界には必要なのだ。ところが、「権威ある雑誌」を自負するものは、そこに載せる情報すら選別しようとする。音楽ホールの中にも利用者を選ぶ所があるが、利用したい人には利用させるべきである。そこから未来がまた膨らむ。 「○○誌に載ってないから知らなかったんだけど、たくさんやってんだあ〜、何で載せないの?」と聞かれることがよくあるが、もうチケットが売れていて宣伝する必要がないのに、「活躍してます」という見栄と近況報告のために広告するのは無駄だと思う。何らかの権威がその本にあると思うから、無駄でも載せなければという観念になる。また、私は自分のコンサートには批評家を招待しないことにしている。批評家は聴くのがビジネスなんだからチケット代は確定申告できるし、自己負担は当然のことだ。そのかわり評論家は出版社からもっと高額な原稿料をもらうべきである。そうすることで責任が生じ、責任を果たせない批評家や無用な雑誌はおのずと淘汰されるだろう。聴いてもいないコンサートの批評を書くような人もいなくなるだろうし、演奏家もチケットが売れることになる。招待するなら普段聴く機会を持てない人たちや、心に深い傷や悲しみを負った方々にチケットを差し上げたいと思う。批評家もよりプロフェッショナルとしてのステータスと誇りが持てるだろうし、ビジネスとしてそれぞれが職の場所を獲得するために何をすべきか、何をすれば道が増えていくかを考え、個人の主観だけでなく、「自分が業界の一部なのだ」という自覚も生まれてくると思う。
では、聴き手の方はどうだろう? クラシック低迷が言われている中、本当に楽しみとして聴いてくださる方が増えてきているのも事実だ。アイドルのコンサートに行くノリで、我々のリサイタルや室内楽に来て貰えたらいいのに・・・・・と思う。音楽が人生の中心にあるというより、人生を彩る素敵なアイテムとして利用して欲しい。音楽を愛するとは、音楽が自分の傍らにあるということではないだろうか? それでこそエンターテインメントの需要と供給のバランスが保てる。確かに、「こうあるべきだ」と思いこみ、力んで聴くのも聴き方の一つだし「プロは批評されて当然、金を払っているのだから」と言いたい放題にするのも、ある意味で正しい。が、はっきりいって、そんなお客の前で夢のある演奏ができるはずがないじゃないですか(笑)。できるとすれば、それは聴き手を無視して、自分のためだけに弾いているのです。「金を払ったんだから」とか「こういうことをやりたい」ということだけで高級クラブに乗り込んで、そこの女性に好き放題するのが、遊び方としてうまくないのと同じ。私は食べることが好きだからあちこち行くがそれは自分の物差しに合うものだけを探している訳ではないし、たとえまずいものに当たっても、出会う楽しみのためにお金を払ったと思える。本当にお金がいる人は宝くじを買ったりしないだろう──これもまた愉しみのうちなのだから。しかし、聴き手を非難するのは間違いだ。音楽を純粋な楽しみとして享受できない聴き手を作り出してしまうのは、音楽を純粋な喜びとして表現できなかった私たち演奏家の責任でしかない。

よし、まだ若いのだ?
こう言われたこともある。「斎藤君は若いね、戦うなんて。そう思っていても、いつか自分が批判した人と同じような人間になってしまうのさ」と。どうも実るほどこうべを垂れる稲穂になるのは難しいらしい。しかし現役で舞台に立っていれば、謙虚さを失うことはありえないし、常に人と向かい合い、音楽に接していく姿勢を維持できるはず。音楽が好きだし、人との出会いも大切にしている。心から愉しんで演奏でき、少しでも多くの人と本当の音楽の喜びを分かち合えますように精進したい・・・・・。
そう、まだまだ若いよ。 よし、またがんばるのだ! よろしく!
