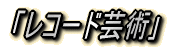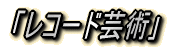|
(発行:(株)音楽之友社/TEL:03−3235−2122)
 2009年1月号 (p.192) 2009年1月号 (p.192)
ザ・スーパートリオ
ソプラノ、クラリネット、ピアノという組み合わせ。さまざまなポピュラー音楽をメドレー風に聴かせるアルバムだ。カルメン・メドレー、ポーギーとベス・メドレー、星のメドレー、さらにジュディ・ガーランド・メドレーなど。そのための編曲に意を凝らし、たがいに気心の知れた仲間同士のノリでザーフィンをたのしむようにそれらをつぎつぎに軽快にこなしてゆく。
ディナー・ショーでつぎつぎに出てくるコース料理をたのしにながら聴くという趣もあるが、むしろ通だけが知っている巷のちょっと見つけにくいカフェ・バーの雰囲気に近い。ほの暗い照明、入りにくそうだが、思い切って覗いてみるとパッとはじける音楽と笑顔に迎えられ、あっというまにそのなかに融け込んでしまう。使い込んで飴色になったカウンターや棚、テーブルや椅子のなつかしい感触。それらとザ・スーパートリオの音楽とのあいだにはなんの違和感もなく、自分がはじめて音楽のたのしさに開眼した時代へタイム・スリップする。クラシックやポピュラーの区別なく音楽を音楽として先入観なくたのしんだ時代。メドレーがつぎからつぎへと繰り出され、青春時代の思い出がそれに合わせて走馬灯のように浮かび出てきて、なつかしさで心がいっぱいになる。どこかで見た風景。村上春樹のピンボールの出てくる小説の1シーンと重なりはしないだろうか。
 2003年6月号 (p.54-55) 2003年6月号 (p.54-55)
ロマン派時代のピアノ音楽〜斎藤雅広、ピアニストたちのアプローチを語る
★テーマ曲「ショパン:バラード第1番」
思い思いにショパンを表現していた第1世代のピアニストたち
今回聴いたなかで一番古い録音は、1928年のコルトーのディスクです。コルトーには33年のものもありますがスケールが大きく、自分の感情を情熱的にロマンティックにぶつけて行く演奏スタイル。29年のブライロフスキーも37年のホフマン、38年のモイセイヴィッチも同様なアクが強いスタイルで、一見我流でありながらもショパンの心も伝え、ショパンの様式から逸脱していない所が見事だし、厚みのある説得力のある演奏でした。彼らに共通する要素は、音楽の上に人間の「悲しい」「寂しい」「うれしい」等の感情を訴えてくる所でしょう。ミスタッチがあってボロボロでも現代に生き続けるのは、ショパンの自然発生的な音楽への共感があるからで、例えばカサドゥシュの演奏(60年)がやや平凡なのに胸を打つ充実感があるのも、この時代の要素を受け継いでいるからなのです。
その点「感情」より「味」で勝負のバックハウスは、純粋に“バックハウス”流でショパンのエッセンスが少なく、彼の個性そのものになっています。演奏が遺っていたらローゼンタールやラフマニノフもこのスタイルになるはずですが、ピアニストの個性と曲の個性の合致というのも、当時はより重要なことだったのです。
ホロヴィッツの47年のモノラル録音は超名演の1つで、ソフロニツキー等に流れるロシア人が弾くショパンの頂点を感じさせます。後のS・ネイガウスやキーシンまでにも、格こそ違えこのカラーは受け継がれています。スケールが大きくて歌い口が憂鬱濃厚なそうしたスタイルに、ホロヴィッツがスパークする巨匠達の流れを充分に受け継いでいるのは、技術が衰えてからの英国の録音で明らかになります。ショパンの音楽に自己の「悲しみ」や「切なさ」を投影させていてすばらしい。ショパンの音楽はベートーヴェンのように計画的で演出を考えた音楽ではなく、即興で生まれ出てきたような心からの自然発生的な音楽なので、演奏家達が独自の方法と感性で迫っていくと、実にエキサイトな効果を生むのではないでしょうか。
ミケランジェリの登場、高度成長期へ突入
そういう自然発生的で即興性の強いショパンの音楽を、あらすじが決まっていたように冷徹に見通して、しかも感動にまで高められたのはミケランジェリだけですね。57年のライヴでは流石に気がはやって平板な感じがしますが、グラモフォンへの録音、晩年のライヴに至ってはテンポ設定や歌いまわしまで全てが理想的です。演奏史の上でも後の人たちにとても大きな影響を与えました。モラヴェッツやグルダの妙に冷静なアプローチや、ホロヴィッツの2種のカーネギーでのライヴの不自然さ等にも、実は大きく影を落としているのです。ミケランジェリは研ぎ澄まされたピアニズムを前面に出して“ピアノ演奏”としての善し悪しで勝負に出ました。このやり方は現代のピアニストの考え方の一つの基本となりました。
このミケランジェリに対抗できたアプローチはリヒテルとギレリスのみです。リヒテルの集中力の高い60年のプラハ・ライヴも名演ですが、65年のギレリスのモスクワ・ライヴは、心技一体の超名演です。オーソドックスな解釈で理想的な演奏を展開しています。奥深い情感もあり、日本の評論家はシフラ等にもそうでしたが、見識があるように振舞いたいがために、技巧派のピアニストをなかなか高く評価しませんでしたが、ギレリスは音楽に対して非常に教養のあるバランスのとれたピアニストです。この二人の演奏は、まるで高度成長期の日本のような勢いがあります。ショパンの作品には、人間の感情のいろんな要素が不定期な形で出てきますが、それをくまなく表現するには、全ての意味でパワーがとても必要とされるということで、以前の巨匠たちにはない現代人の生命力でそれに応えたと言えるでしょう。その裏返しとしてギレリスのヘルシンキでのバラードや晩年来日したリヒテルからは、そうした輝きをもう見出せなかったのも事実です。
他の演奏家は多分に前時代を引きずっていました。アラウの52年の録音は70年代の録音とは雲泥の差の超名演。しかし若き日のアラウも愚かなわが国の評論家には理解できない存在でした。今のクラシック界の低迷は演奏家の責任と謙虚に受け止めていますが、評論家にも身を恥じていただかなくては。このアラウはロマンティックかつピアニスティックで、過不足なく感動的です。同じくルービンシュタインもスケールが大きくてロマン的な演奏が見事で、通常のものの他に最近ライヴも復刻されました。しかし彼の演奏には加えてパデレフスキからの伝統の流れを、その歌い回しの大きさに見出せます。これはポーランド人独特のもので、マルクジンスキー、パレチニ、ステファンスカ等ポーランド人ピアニストの中にもあり、ショパンを叙事詩のような音楽としてとらえ、なよなよしたセンチメンタルではなく、音を大きく打ち鳴らして男のロマンを描いていく感じです。また ショパン弾きとして名高いフランソワは個性的ですが、2種の録音はいずれもテンションも高く、情熱的なコルトーの影響をより強く感じさせます。
情報化社会である現代の演奏
昔の人たちの演奏を情報としてとらえ、バランスよく自分に取り込むのが現代のピアニストの基本。代表はアシュケナージでしょう。欠点なく均整もとれ、いかにも“バラード”は必修科目として勉強したという感じです。個性は違ってもポリーニにも同様です。現在殆どのピアニストがこの感覚のもとに演奏していると言っていいかもしれません。課題を最善にやろうという意識がどこかにあるから聴いていてワクワクしたりしません。技術的に群を抜いているカツァリスやガブリーロフよりも、昔のホフマンの方に興奮します。ツィメルマンに至っては、前述のポーランド人の伝統の継承者としての意識も加わるので、余計に閉鎖的です。そういう意味ではデビュー直後のラーンキの方が自然でしたが、自然なだけでは現代では通用しません。ロシアの伝統を受け継ぐキーシンは、そんな中で独自の事をやろうとの模索を感じさせます。このバラード録音時は「巨匠みたいに弾こう」という意識が働いたろうし、最近のシューマン等にはアムラン達の宇宙的技巧派への挑戦が感じられるし、またそれが作為的でもあったりもします。今回最も今風の演奏だと思ったのはティボーデです。コンクールに出たらとても良い点をもらえるであろう若い人たちの象徴です。オーソドックスでドライで都会的で、だからといって非音楽的なわけでもなくすばらしい。と言いつつ、実は私は昔のゴドフスキーのピアノ・ロールがとてもティボーデに似ていると思いました。自動演奏は機械だけれも、それでもゴドフスキのピアノ・ロールの方が少し味があったりして……。おもしろいですね。やはり現代人は機械的なのかなあ。例えば今は「個性」と言ってもポゴレリチやアファナシエフ等も、決して斬新なのではなく、あくまでも原典と違うようにやるという事なので、原点を意識するということでは普通に弾いてるのと根底は一緒なんですね。現代的な演奏がイヤだといって「昔懐古」を目指してみても、実際にホロヴィッツやルービンシュタインたちのCDも生きてるわけで、彼らにはなかなか敵わない、苦しい立場です。ではある意味「没・個性的」かもしれないが総合的に多角的にハイ・レベルな演奏を目指せばという事になる。確かに全部あるというのは凄い事だけど、かつてのミケランジェリのように「演奏レベルの高さ」で人を感動にまで昇華させるのは、誰もが超絶技巧を持っている現代において果たして可能なのか?こうなってくると、まさに情報化社会こそ、演奏家に迷いを与え個性を失なわせる「音楽芸術の敵」かもしれませんね。
さて《バラード1番》は曲自体の完成度が高いためか、かなり個性的な人たちも表面的ないじりが少なく、逆に本質的なものをじっくり味わうことができて、今回はとても有意義でした。ショパンの音楽はピアノそのものですね。作品に感謝いたします。
 2003年4月号 (p.350) 2003年4月号 (p.350)
独断!こだわりのディスクベスト3
確かに「好み」はこだわりである。これが実は全くいいかげんなものであって、自分の境遇や気分、体調等でいとも簡単に変わってしまったりもする。音楽も演奏も、もともと人格のようなものだから、そこには長所もあれば短所もあるし、接する人によって大きな差異が存在しよう。だから「こだわりの3枚」も、自分のこだわりよりも文句なく惚れそうな物を選んでみたつもりだが、こんなことがまたこだわりだったりしてね。実際のところ海賊盤のようなオペラのライヴを集めるのも大好きで、この際それを列記しようかとも思ったが、一応ピアニストであるので(笑)、まずはピアノから。
1)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番
(P)ウィリアム・カペル(指揮)レナード・バーンスタイン/ニューヨークフィル(1951)
ハチャトゥリアン:ピアノ協奏曲
(P)ウィリアム・カペル(指揮)ユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団(1944)
MUSIC&ARTS CD-1109 (USA)
最近はコルトーにベートーヴェンのほぼ全曲のソナタの録音とか、ホロヴィッツのバラキレフ:イスラメイとか、目を丸くしそうな録音が復刻を待っている状態。実はこのCDも昨年陽の目を見た、伝説のピアニスト・カペルの凄演である。すでに、ラフマニノフはレギュラー盤でスタジオ録音の名盤があるし、トレードマークだったお得意のハチャトゥリアンなどは、私自身でさえこの他に3種類も持っている。しかし今回は共演者も良いし、音の状態も良好ということで聴きごたえも十分、カペル自身も調子よく、最近聴かれなくなった情熱的な燃える演奏でありながら、現代的なピアニストの香りも共存しているあたりが素晴らしい。ハチャトゥリアンでの「キレ方」もなかなか楽しい。他にもラフマニノフの3番やブラームスの1番等、カペルのスリリングなライヴの復刻は絶えず、人気も衰えず・・・そう言う意味では今後も多いに楽しみであるが、この人が長く生きていたらピアノ界もかなり変わったと思う。
2)ラヴェル:ピアノ協奏曲
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第4番
(P)アルトゥーロ・ベネデッティ=ミケランジェリ
(指揮)エットーレ・グラシス/フィルハーモニア管弦楽団
EMI CDC7ー49326ー2 (GERMANY)
たまたま私のものが輸入盤だったが、これは国内盤でも何度も登場しているありふれた1枚で、しかし言わずと知れたミケランジェリ一世一代の大名演。「ピアノ」という楽器の最高の音と演奏技術、それがかくも上品に、心と叙情性を失わずに表現された理想郷の1つだ。余談だがラヴェルの方は何種類かライヴの入手が可能で、チェリビダッケとのものも素晴らしい。ラフマニノフは記録によると、このスタジオ録音に先駆けて行われたコンサートで、ミケランジェリは腱をつりながらも凄い演奏をしたそうで、以前私はチェトラのレコードでそれらしき物を見たことがあったのだが・・・。買って置けば良かったなあ・・・どなたか持ってませんか?
3)ゼ・エッセンシャル (Br)ピエール・ベルナック
(P)ジェラール・ムーア、フランシス・プーランク、グラハム・ジョンソン他
SBT 3161(3枚組) TESTAMENT (ENGLAND)
フランス歌曲の神様ベルナックの録音を集めたもので、副題にその友人たちとあるが、有名なプーランクとのコンビネーションで聴かせるフランスものの素晴らしさは「音楽を少しでも演奏しようと思ったら、ここに学ぶべきものがいっぱい詰まっている」・・・そんな極意と「表現力とはそもそも何か」といったようなものを見せつけてくれる、ジャンルを超えたバイブルのようなものなのである。またカザドゥシュとの録音もあるが、ここでは若きムーアとの「詩人の恋」も聴けて、これがフィッシャー=デーィスカウの「変だけどうまい」ドビュッシーの歌曲の様で、なかなかに楽しめる。グノーのセレナード1曲でもその表現力の多彩さにノックアウトされよう。日本ではベルナックの芸術が知る人ぞ知るというレベルにあることがとても悲しい。かってアラウもシフラも過小評価されていたし、山根銀二氏は「エドヴィン・フィッシャーのシューベルトは、技術偏重で音楽性が微塵もない」と断言していた(笑)。諺によると「評論家の銅像が立ったためしはない」らしいが、後始末もされないのでは演奏家が浮かばれない。
|